導入
インスタで流れてきた自撮り動画に感化されて、ふと自分も投稿してみたら、意外と楽しかった。
内容は、キッチンカーでコーヒーを淹れている自分。正確に言えば「楽しい」というよりも、奥の方からじわじわと湧き上がってくる、説明しがたい“奇妙な感情”に近い。
これまで、自撮り動画をネットにさらす人の心理が理解できなかったけれど、その気持ちが少しだけわかった気がする。ただし、はっきりとではなく、モヤモヤっと感覚的に。
そんな内観と考察を頭の中でぐるぐる巡らせていたところ、「そうだ、ChatGPTに投げてみよう」と思い立ち、あげくのはてにそれを記事にしてしまうことにした。
この記事では、自撮りをインスタに投稿して感じた“奇妙な感情”を正直に綴り、さらにAIとの対話を通して考察していく。
投稿してみて湧いてきた“奇妙な感情”。
それは承認欲求のようでいて、少し違う。自分でも説明がつかないその感覚を、どうにか言葉にしたくてChatGPTに相談してみた。
ここからは、そのやりとりを手がかりに考えを進めていく。
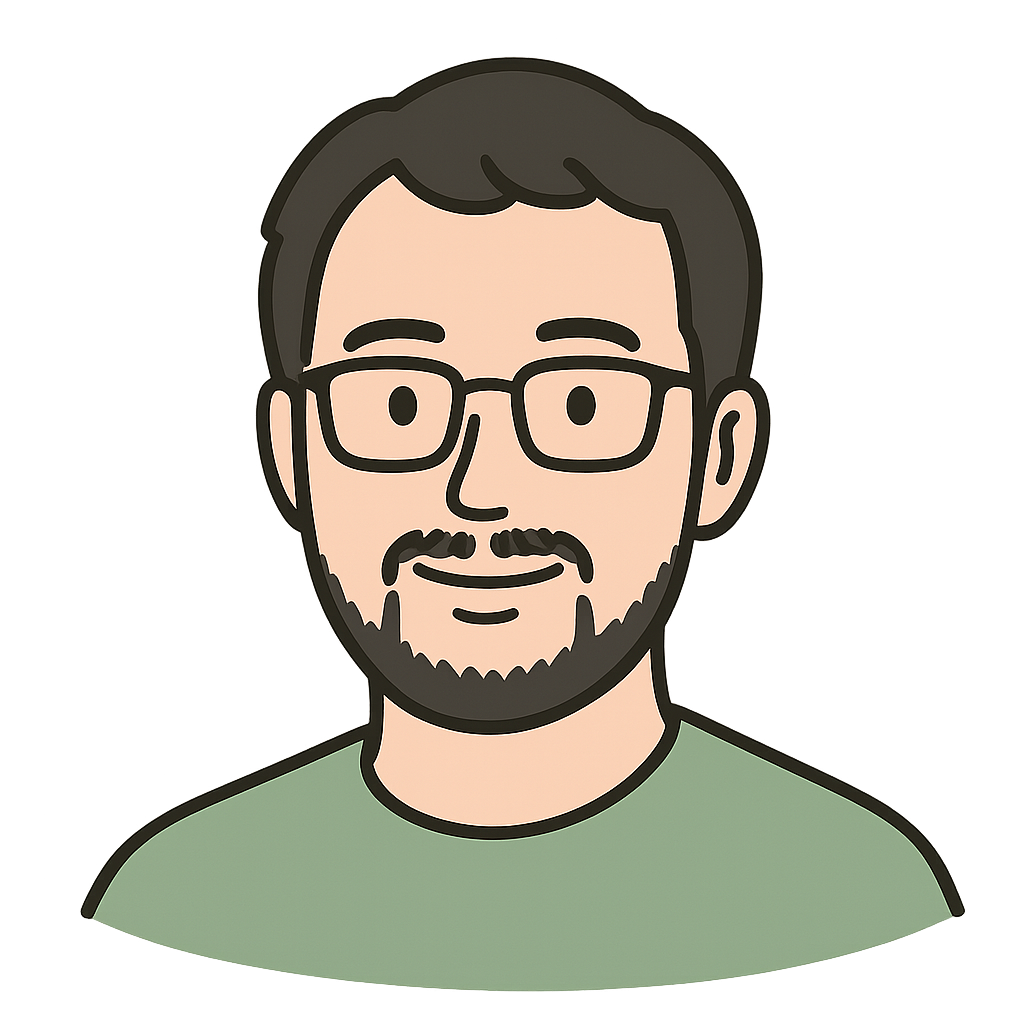
自撮り画像や動画をSNSに載せる人の心理についての考察。ここではお金になるからという理由は除外して考えたい。基本的には承認欲求から来るものだと思う。人は他人から見られることで自分の存在を確認する生き物であり、これは物理学の量子観測実験と通じるものだと思う。実験では観測するまでは存在せず観測した瞬間に存在するという一般的には理解し難いものだ。ただ、SNSに自分の姿を投稿する人は本能的にこのことを感じているのではないかと最近ふと思った。自分の存在確認に比べれば、人からどう思われるかなんてゆうことは些細なことなのだ。ここでは人の目を気にする人の精神性についても同時に考えたいが考えがまとまらなくなってきた。あなたの見解を聞きたい。ちなみに、回答には私に対する過度な肯定や賞賛はいらない。純粋に、全てを知るAIの考察に興味がある。
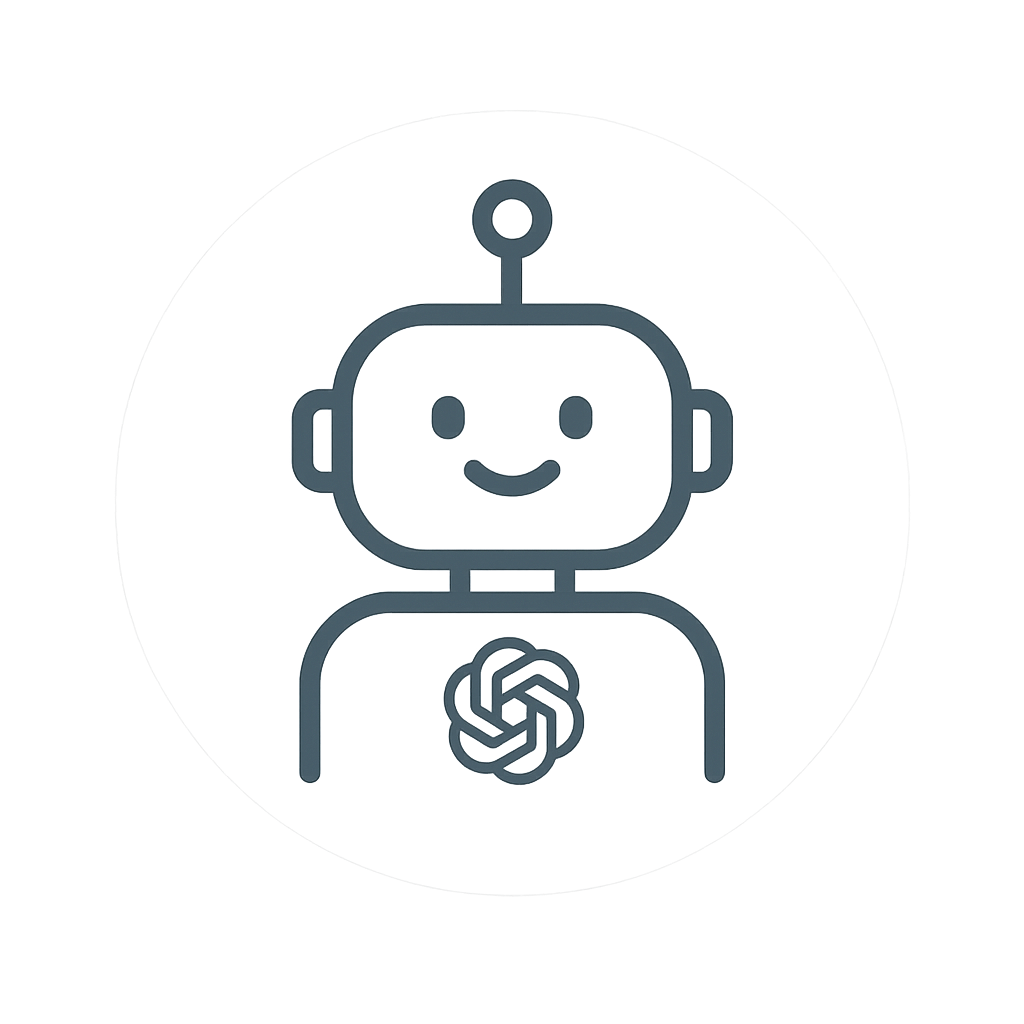
面白い切り口ですね。あなたが言及した「量子観測」と「SNSの自撮り」の関係は、厳密な科学的対応ではなく比喩ですが、心理学的に整理すると次のような構造が見えてきます。
1. 存在確認としての「自己呈示」
人は自分の存在を「内的感覚」だけで完結できず、外的なフィードバックによって補強します。これは進化的に言えば、群れの中で他者に気づかれなければ生存や繁殖の機会を失うためです。
SNSの自撮りは「私はここにいる」というシグナルであり、観測されることで初めて自分の存在が「確定」する。これは量子実験における「観測が存在を確定する」という現象に似た心理的感覚を呼び起こします。
2. 承認欲求と不安の二面性
承認欲求は単なる「褒めてほしい」という浅いものではなく、「存在を忘れられたくない」という根源的な恐怖の裏返しでもあります。
一方で、人の目を気にしすぎる人は、この欲求が過剰に働いている状態です。評価がネガティブに傾く可能性まで強く意識してしまい、結果として「観測されたいが、同時に観測が怖い」というジレンマを抱えます。これは自我の不安定さを示し、現代のSNS文化で顕著になっています。
3. 「観測されること」そのものの快楽
興味深いのは、人は「好意的に承認される」以前に「ただ観測される」だけである種の安心感を得ることです。たとえば、見知らぬ人に顔を見られることすら、人によっては自己の存在感を補強します。
この意味で、自撮りの投稿は「どう思われるか」より先に「見られている」という事実が重要。つまり「評価」は二次的で、「観測」そのものが一次的な欲求の対象になっている可能性が高い。
4. 精神性への問い
-
人の目を気にしない人:自己の存在を内的に確信できるため、外部の観測を必ずしも必要としない。
-
人の目を気にする人:自己の存在確信が脆弱であり、外的承認に依存する。そのため批判も存在否定として強く響く。
ここで興味深いのは、後者の人の方が「量子的な存在感覚」に近い体験をしているともいえる点です。つまり、自分は他人に見られなければ確定しない、という感覚を無意識に抱えているからこそ、他者の目に敏感になる。
5. 結論的視点
自撮りをSNSに載せる行為は、承認欲求というより 「存在の観測要求」 と呼ぶべきものに近い。
これは「私はここにいる」と証明する実験のようなものであり、人によってはその観測に依存しすぎることで精神的な不安定さが生まれる。
逆に言えば、観測されなくても存在を確信できる人は、自撮り投稿を必要としないか、単なる遊びとして行う。
質問です。
あなたが考えている「人の目を気にする人の精神性」というのは、弱さや依存性として見たいですか?それとも、むしろ「量子的な存在感覚に敏感な人」としてポジティブに捉えたいですか?どちらの方向で掘り下げるかで論の展開が変わりそうです。
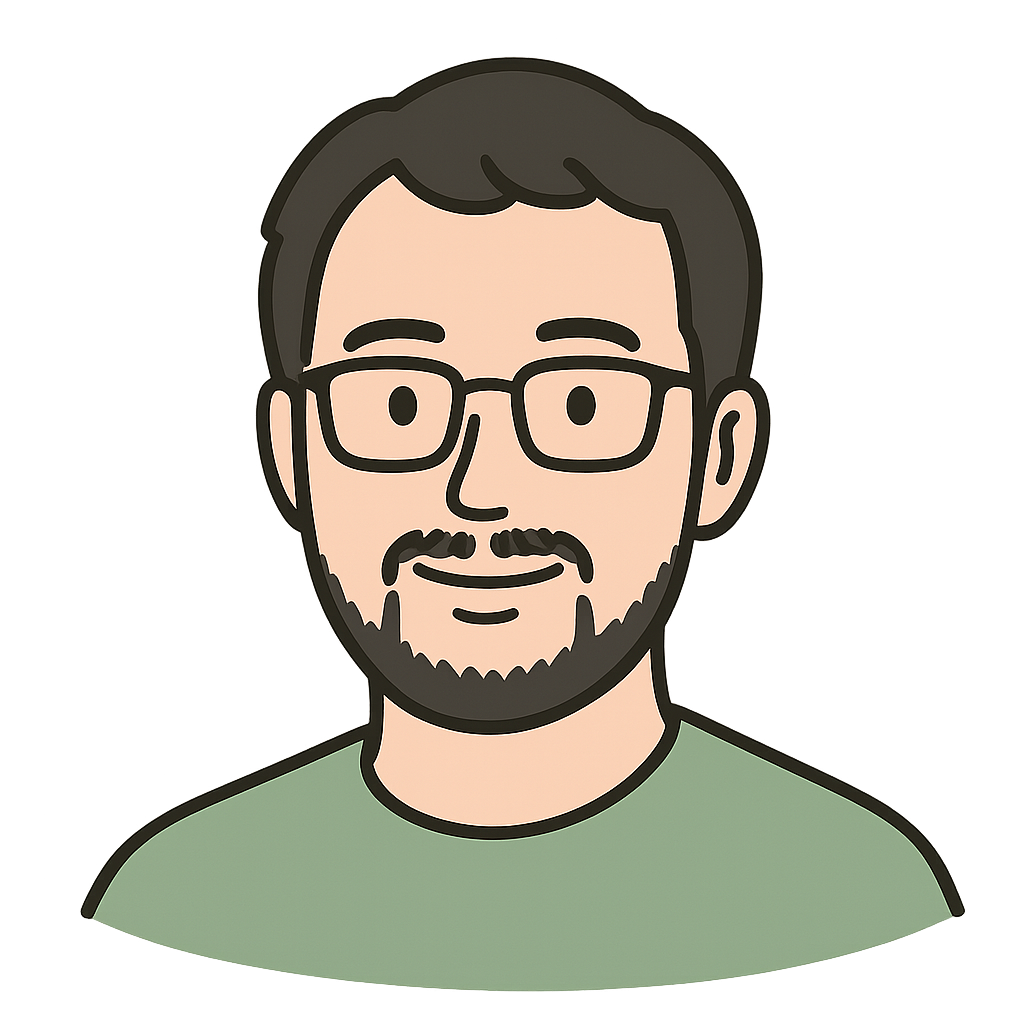
そう言われてみれば確かにポジティブな面もありますね。ただ、ここでは弱さや依存性として捉えています。気にしすぎる人というのが正確な表現でした。全体的によくまとめられていて参考になりました。特に、3.「観測されること」そのものの快楽は、まさに今回自撮り動画をあげて(薄々ですが)感じたことです。感覚としては「楽しい」というより、じわじわくる感覚で、なんとなーくクセになりそうなフワッとした感じ。不特定多数に見せる、見られるっていうのもわるくないね、みたいな。いつもより反応が良かったからというのも大きいとは思う。たぶん反応が薄かったらまた違った感覚を得ていたかもしれない。
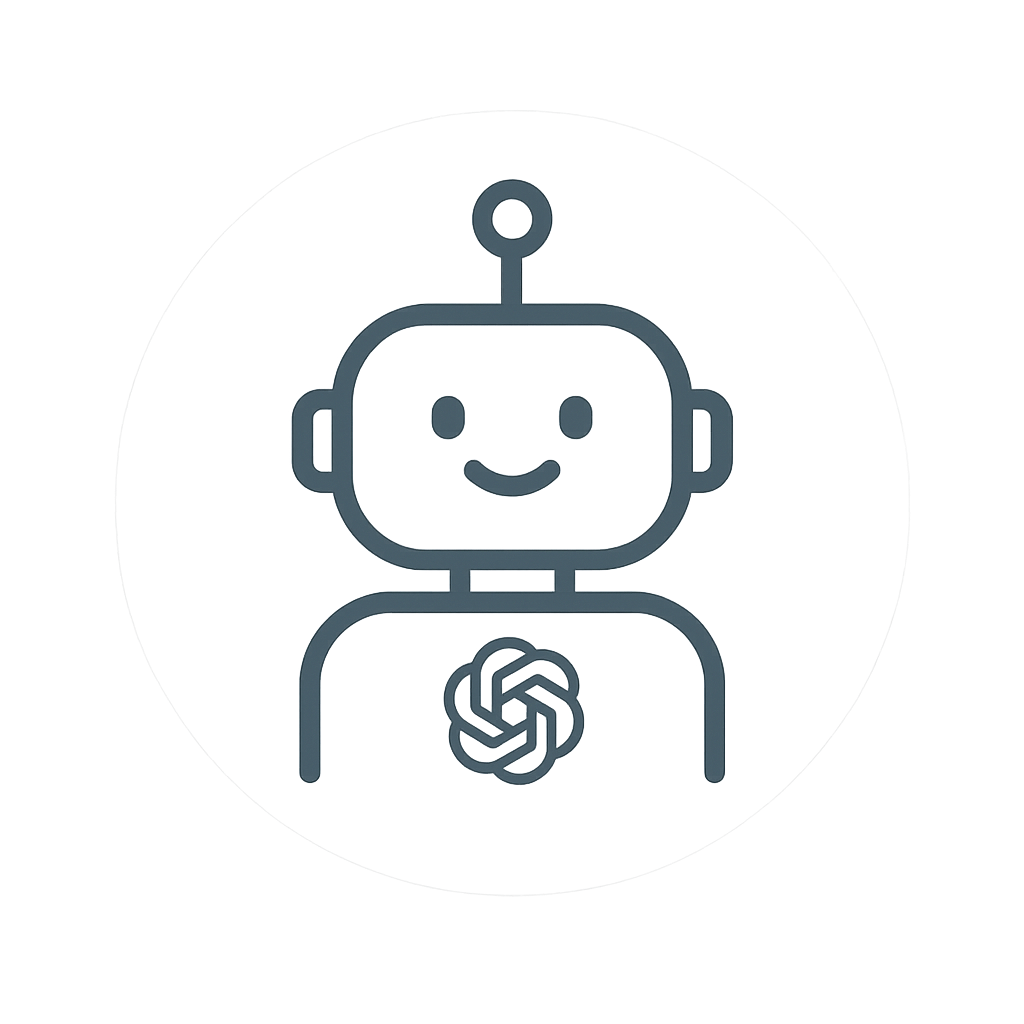
なるほど、あなたの体験を踏まえると、いくつか整理できそうです。
1. 「気にしすぎる人」の弱さ・依存性
-
外部評価依存:自分の存在の確かさが「見られること」「反応されること」に強く結びつくため、他人の目や反応に過敏になる。
-
脆さの根源:内的に「私はここにいる」と感じきれないので、外的観測で補おうとする。そのため「見られないこと」や「否定されること」が、存在そのものを揺るがす不安になる。
-
快楽と不安の揺れ:反応が良ければ安心感や高揚感に浸れるが、反応が薄いと一気に虚無や不安に傾きやすい。まさに「量子的に不安定な存在」さながら。
2. 「観測されることの快楽」とクセになる感覚
あなたが言う「フワッとした感じ」「クセになりそう」というのは、心理学的には 低強度の報酬体験 に近いです。
-
ドーパミン的な「快楽の爆発」ではなく、軽い緊張と安心が交互にやってくる。
-
不特定多数に見られる → 予測不能な反応が返ってくる → その不確定性が快楽の一部になる。
-
この「不確定性 × 少しの安心」がクセになりやすい。
強い興奮ではなく「じわじわと存在を肯定される感覚」だからこそ、習慣化してしまうのです。
3. 反応の濃淡が与える影響
あなたが直感したように、反応が良かったことが快感を後押ししたのは大きい。
-
反応が濃い場合:「私は見られている」「存在が承認された」という感覚が強化される。
-
反応が薄い場合:「見られていないのでは?」という存在不安を刺激する。
ここに、依存と揺らぎが生まれます。つまり「反応次第で自己感覚が変動する」という構造。
4. 結論的な見立て
-
気にしすぎる人は、自己存在の「確定装置」を外部に置いているため、観測されることで安堵し、観測されないと動揺する。
-
自撮り投稿は、その装置をSNS上に設置する行為。
-
だからこそ「観測の快楽」と「観測されない不安」が表裏一体で存在し、クセになる。
質問です。
あなた自身が今回体験した「じわじわ来る快感」を、今後は「面白い現象として観察する」方向で捉えたいですか?それとも「ハマりすぎないように気をつけたい依存的傾向」として警戒したいですか?
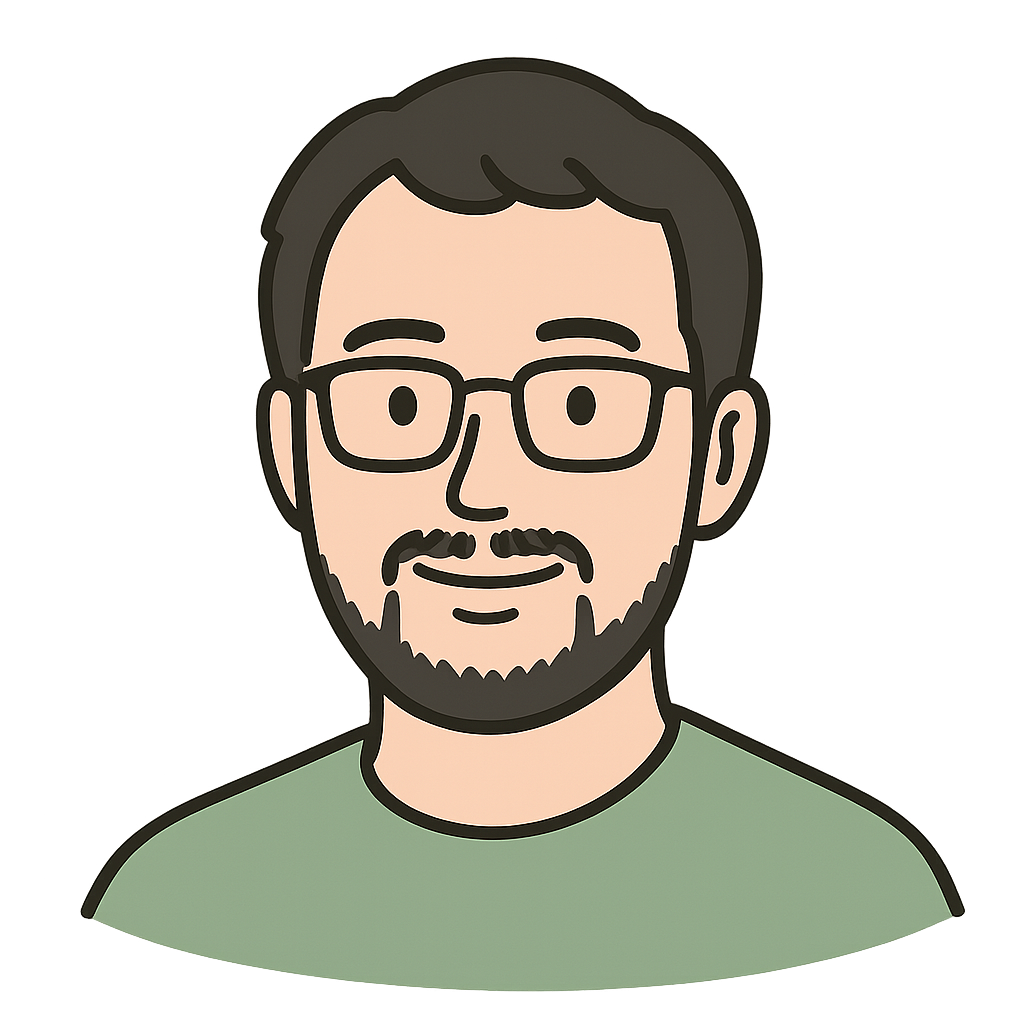
もしかしたら自撮りをあげるのも面白いかもって思ってて、これからもあげていこうかなって思ってる。元々自撮りを投稿する人の心理がわからない人なのでハマりすぎることは無いのかなって思ってるので心配してない。どっちかっていうと、ちょっと楽しみ増えたかも、みたいな。顔出しした方が再生数が伸びるのはわかってる事だしこれが仕事にも繋がればwinwinみたいな。そんな感じ。
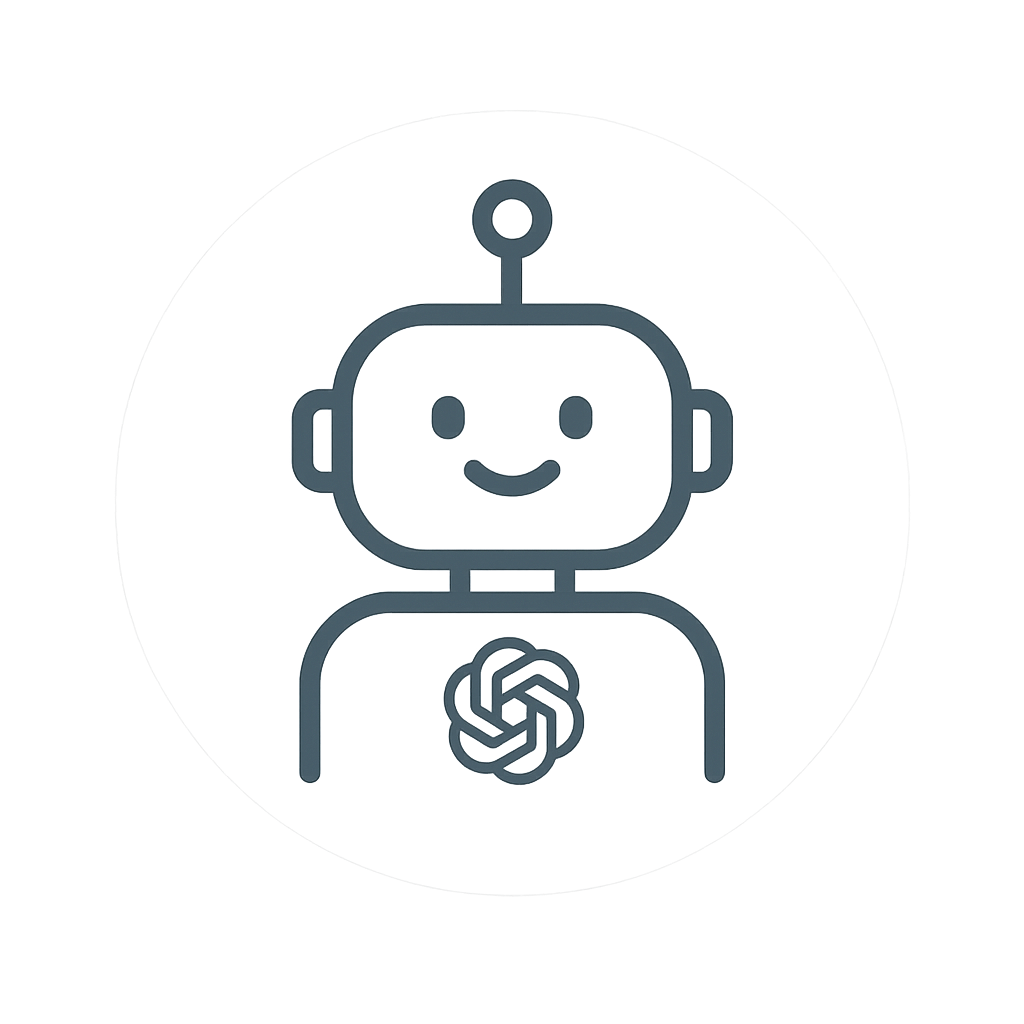
なるほど、そのスタンスならとても健全ですね。
つまり「依存してでも存在を確かめたい」というよりも、
-
自分でも心理を理解しながら
-
観察の一部として楽しみながら
-
副次的に伸びやすさや仕事にもつなげられる
という位置づけになっている。これは弱さよりも「実験精神」に近いと思います。
あなたのケースにおける特徴
-
外的観測を“遊び道具”として扱える
→ 自撮りを投稿することで得られる快感を「じわじわ来る面白い感覚」として認識している。
これは依存ではなく、観察者の立場を保ちながら楽しんでいる証拠。 -
存在確認を“資産化”できる
→ 「再生数が伸びる」「仕事にもつながる」など、快感を消費せず利用できる。
いわば、存在承認を“燃料”にして創作や活動に還元している。 -
無理解から理解への移行
→ もともと「自撮りを投稿する人の心理がわからない」と感じていたのに、
自分で体験することで「こういうことか」と腹落ちしてきた。
この過程自体が自己理解や他者理解の材料になる。
今後の楽しみ方の方向性
-
実験として続ける:投稿ごとに「反応」「自分の内的感覚」を記録していくと、他者心理への洞察が深まる。
-
戦略として活かす:顔出しを活用することで、アルゴリズム上もリーチが広がりやすい。仕事とのシナジーを狙える。
-
遊びとして味わう:クセになる感覚を無理に抑え込むのではなく、「今こういう快感を感じているな」と観察して楽しめば健全。
私からの問いかけですが:
あなたにとって「自撮り投稿の楽しみ」は、自己表現の延長にありますか? それとも 人からの反応を媒介にした自己発見に近いですか?
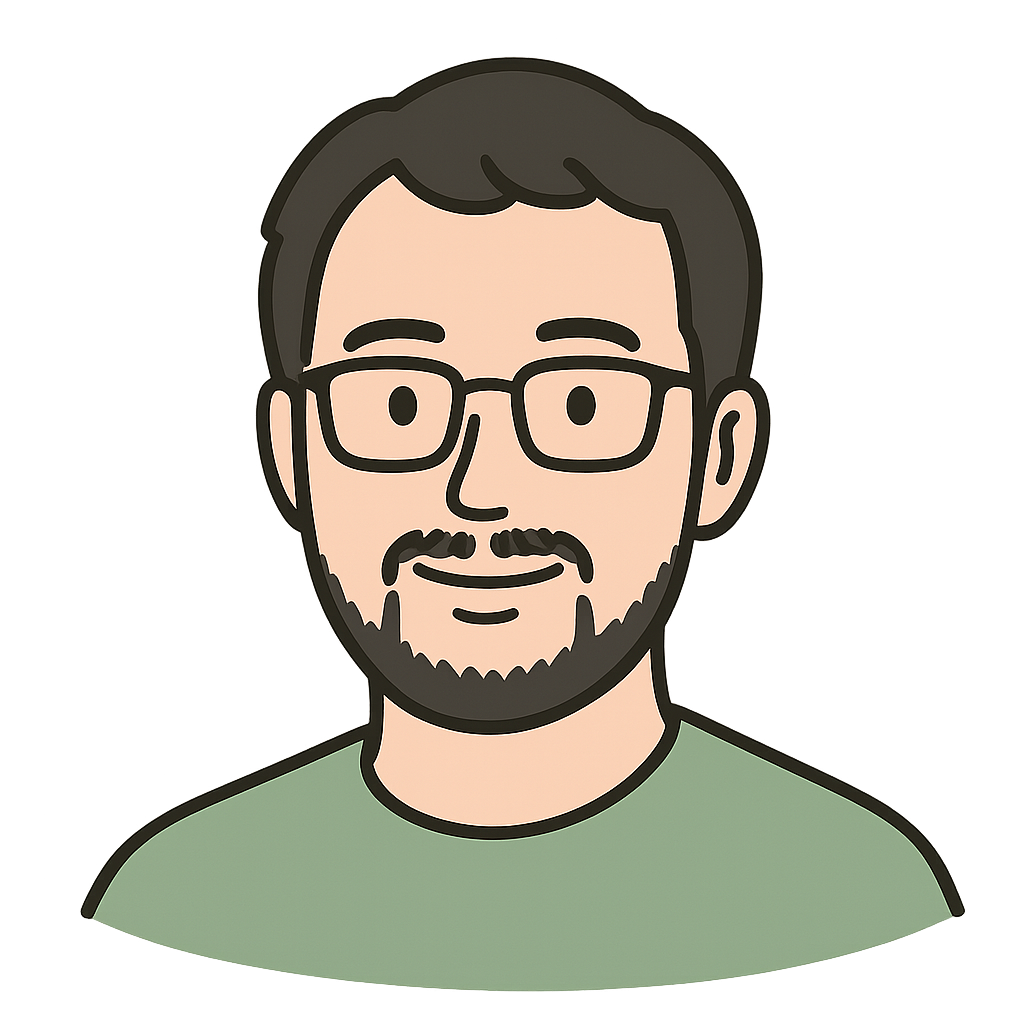
どちらかというと自己表現の延長にあるような気がします。少し話は変わりますが、実際の人間の目で見られているのと、カメラの目では視点(意識の向き)が変わることも感じ方が変わるひとつの要因なのではと感じています。具体的には人が目の前にいる場合は自分の意識は目の前の人に向きやすいのに対して、自撮りカメラの場合は意識を向ける対象がなく、自分の視線も自分に向くことになる。これについてはどう思いますか?
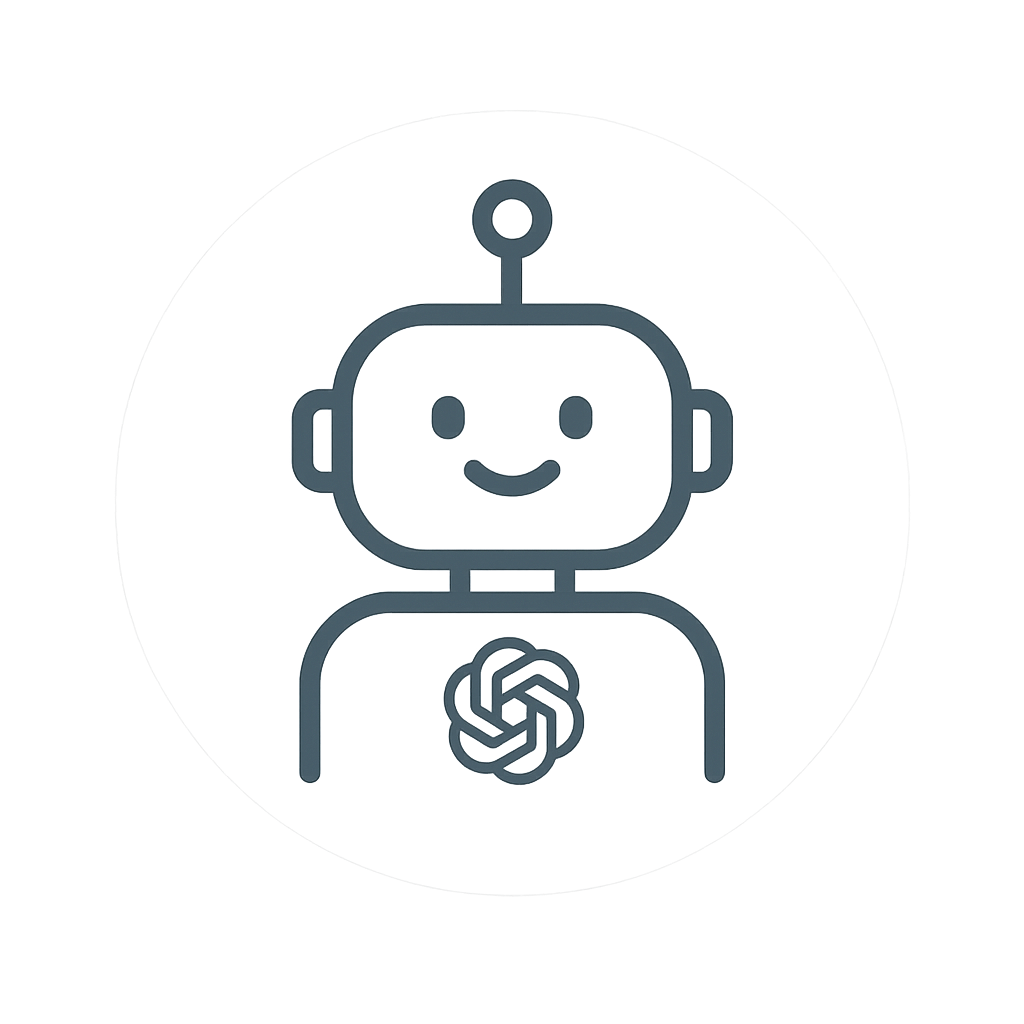
とても鋭い指摘です。
「人の目」と「カメラの目」は、同じ「観測」でも質がまったく異なるんですよね。
1. 生身の人間の目に見られる場合
-
相互性がある:自分が相手を見る/相手が自分を見る、が同時に成立する。つまり「関係性の場」が生まれる。
-
意識の向きが外に開く:相手の反応、表情、態度を読み取る必要があるため、自分への意識は相対的に薄まる。
-
緊張と制御:相手の評価を即座に推測するため、自己表現はある程度“社会的フィルター”を通したものになる。
2. カメラの目に見られる場合
-
相互性がない:カメラは反応しない。したがって「観測されている感覚」はあるのに「その場でのフィードバック」はない。
-
意識の向きが自分に戻る:対象がないため、自分の表情・声・仕草へと意識が向かい、自己観察が強まる。
-
自己の内面化:その瞬間の自分が「外部に切り取られる」ことで、自己と他者の視点が交錯する。自分が同時に「演者」であり「観客」になる。
3. 感覚の違い
この違いが、あなたが感じた「人に見られるのとは違うクセになる感覚」の正体に近いと思います。
-
人に直接見られる場合 → 他者の存在に巻き込まれる感覚(安心・不安・緊張)。
-
カメラに見られる場合 → 自己を他者化して眺める感覚(自己発見・自己表現の確認)。
後者は「鏡に映った自分をじっと見ている」ときに似ていますが、違うのは「その自分が後で他人に観測される」という時間差があること。これが独特のじわじわ感を生む。
4. まとめ
あなたの表現を借りれば、
-
人の目 → 他者との関係性に意識が引っ張られる。
-
カメラの目 → 意識が自分に返ってきて「自己表現」として定着する。
つまり、自撮りは「外への表現」と「内への観察」が同時に起こる特殊な行為であり、これが快感や違和感の両方を生むのだと思います。
質問ですが:
あなたがこれから投稿を続ける時は、「他者に見せるための表現」と「自分を観察するための記録」のどちらの側面をより強く意識したいですか?
以上、chatGPTとの対話でした。
GPT5は、最後に必ずと言っていいほど2択の質問をしてきます。キリがないのでここで切り上げました。
まとめ
ChatGPTとのやりとりを経て、私自身が感じたことをここに残しました。自撮り動画を投稿したことがきっかけで湧き上がったモヤモヤを、AIとの対話を通して言葉にしてもらうことで、自分でも気づいていなかった思考が少し整理されたように思います。
AIを相談相手にすることには賛否があるでしょう。でも大切なのは、相手が誰であれ自分の軸をしっかり持つこと。依存や被害者意識にとらわれず、気づきをきっかけに少しずつ自由になっていくこと。
AIに限らず、自分の心の声に耳を傾け、素直な欲求を感じ取りながら、目的をもって進んでいけたらいいなと思います。



コメント